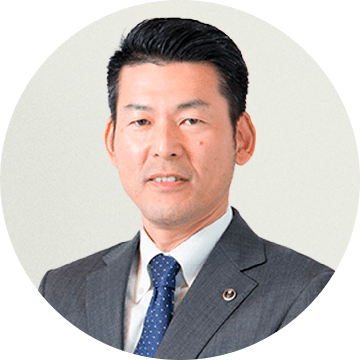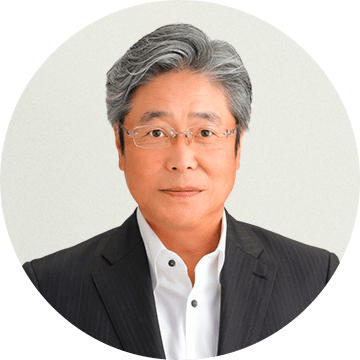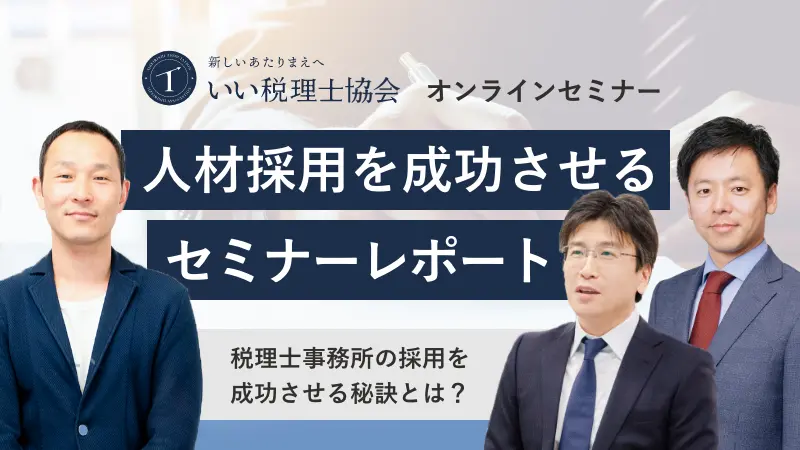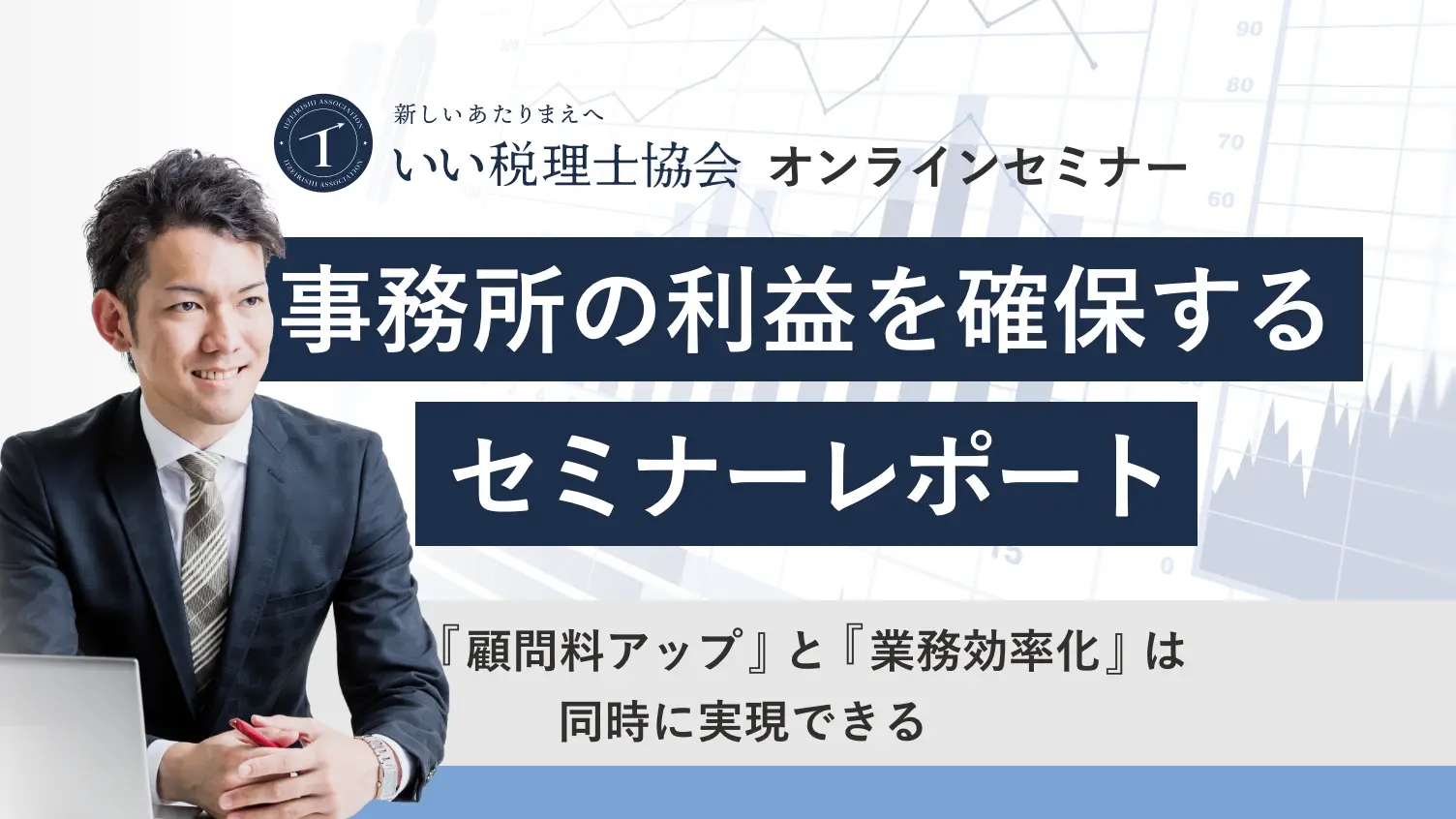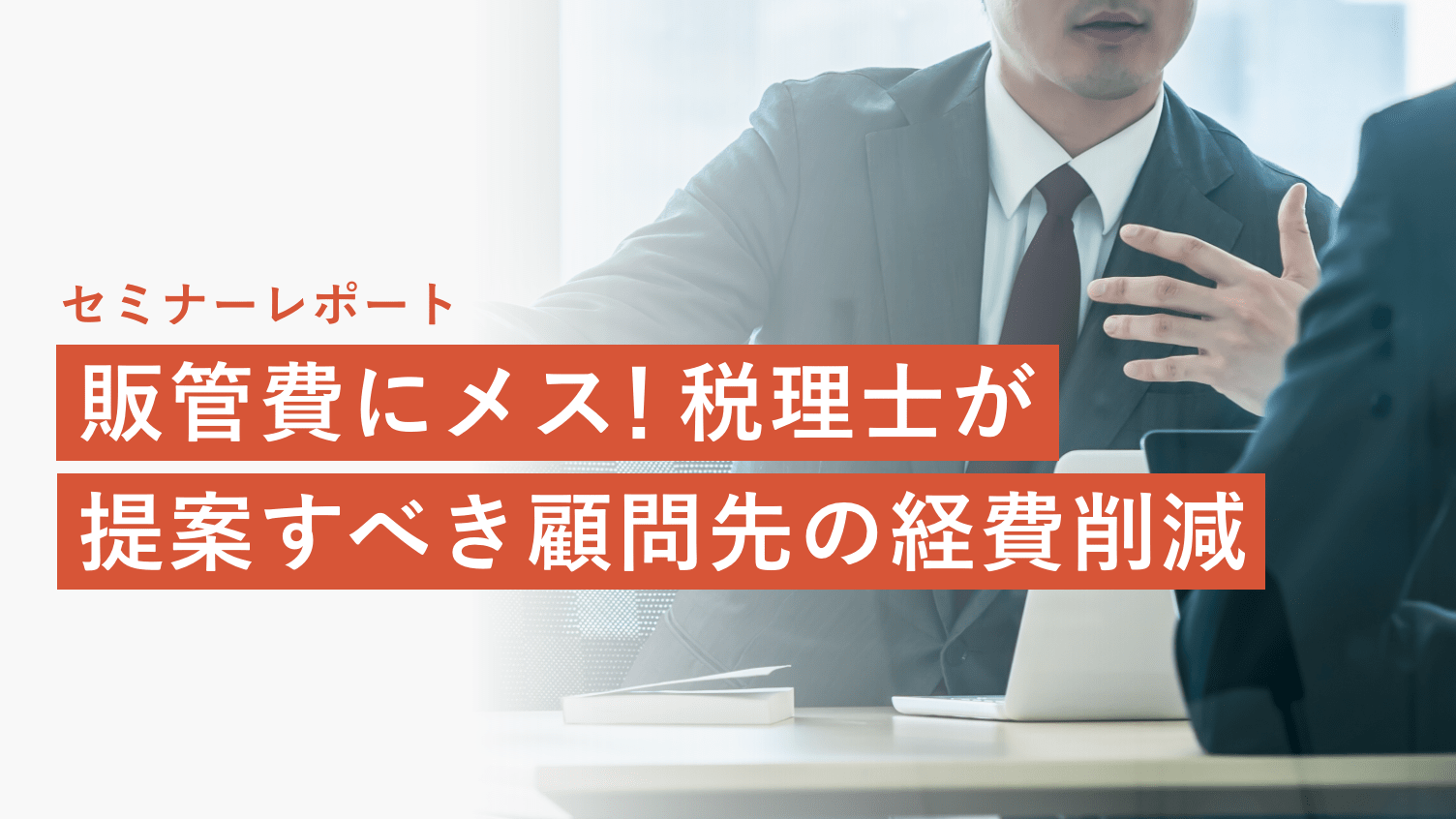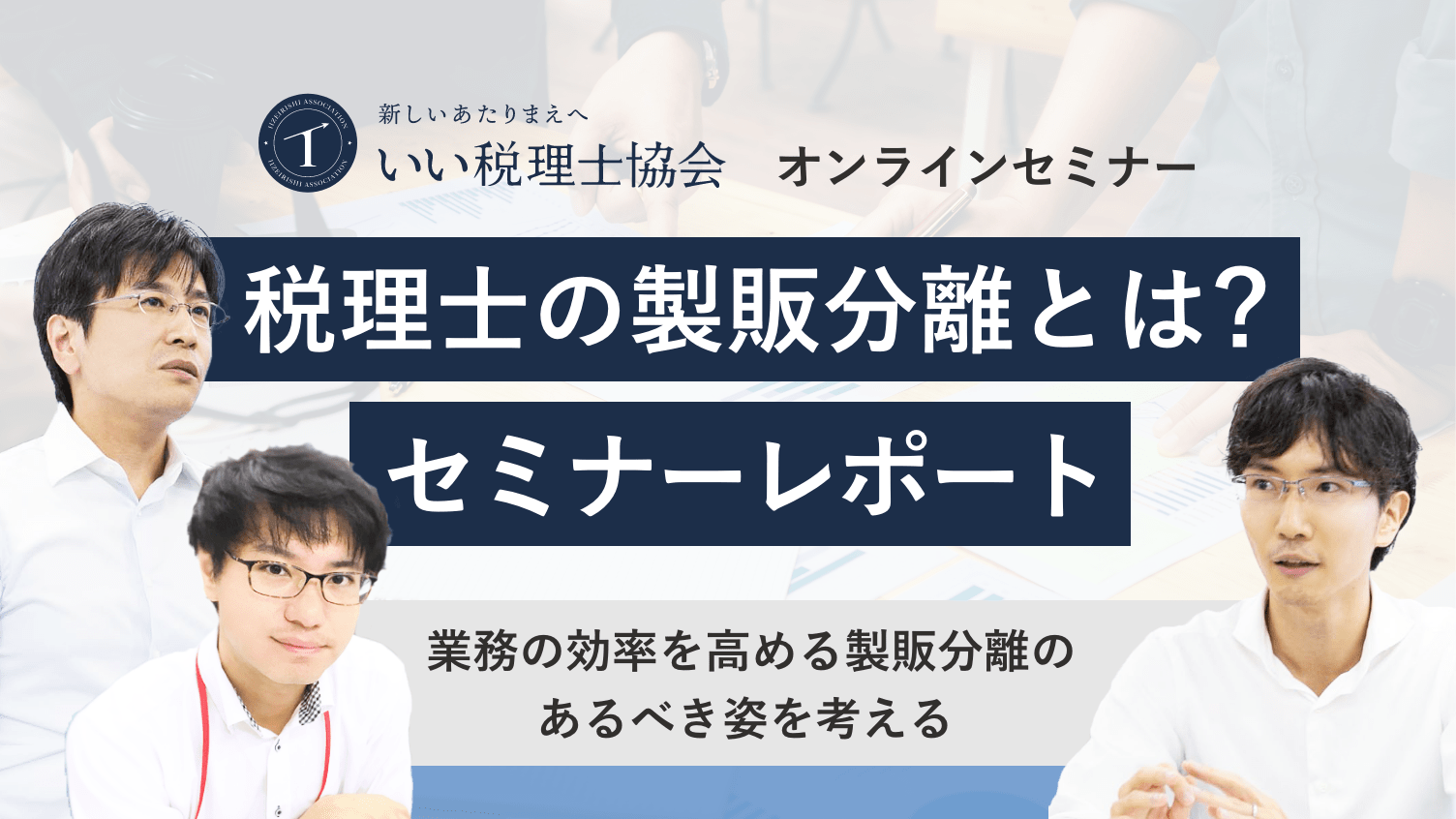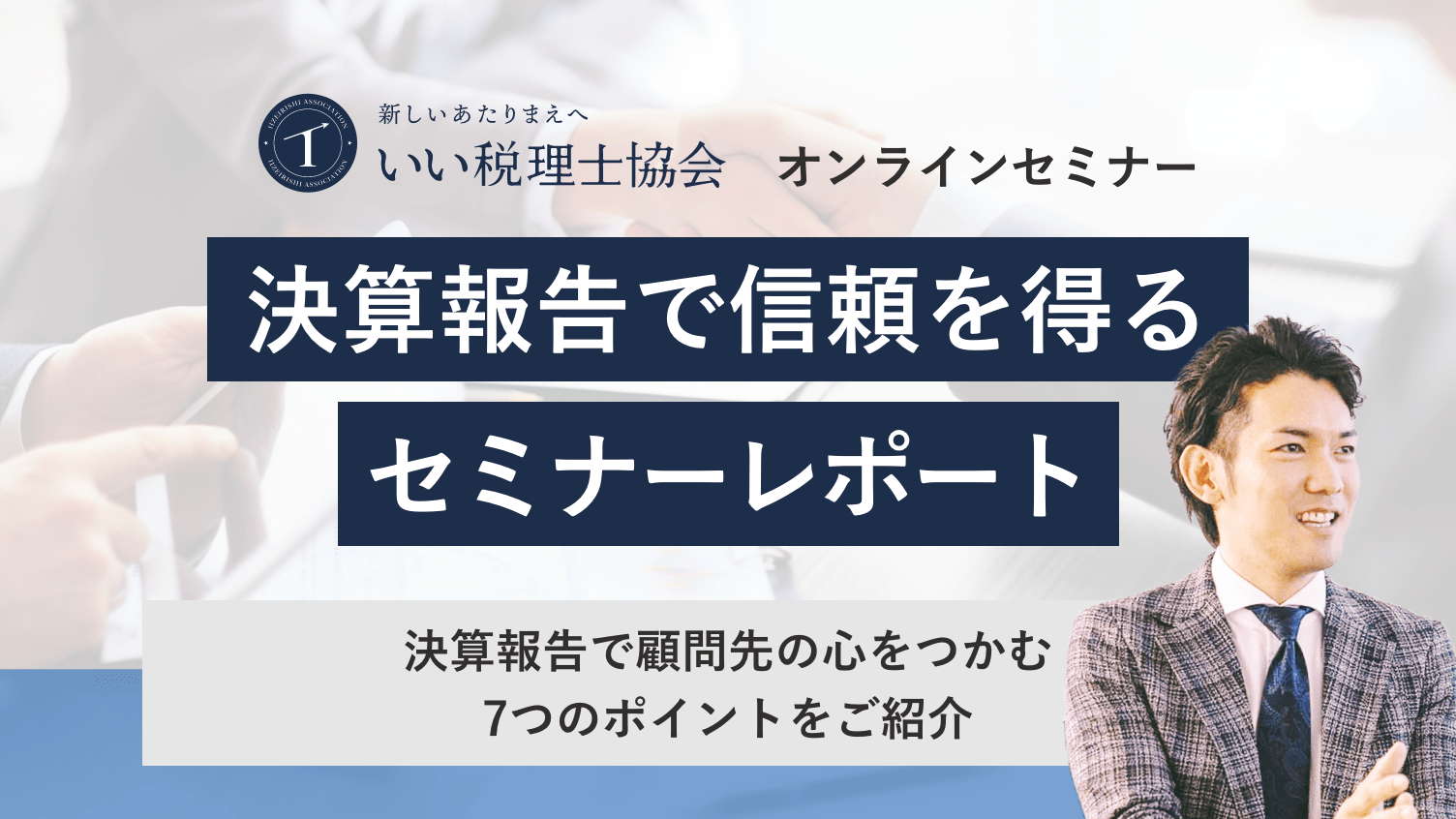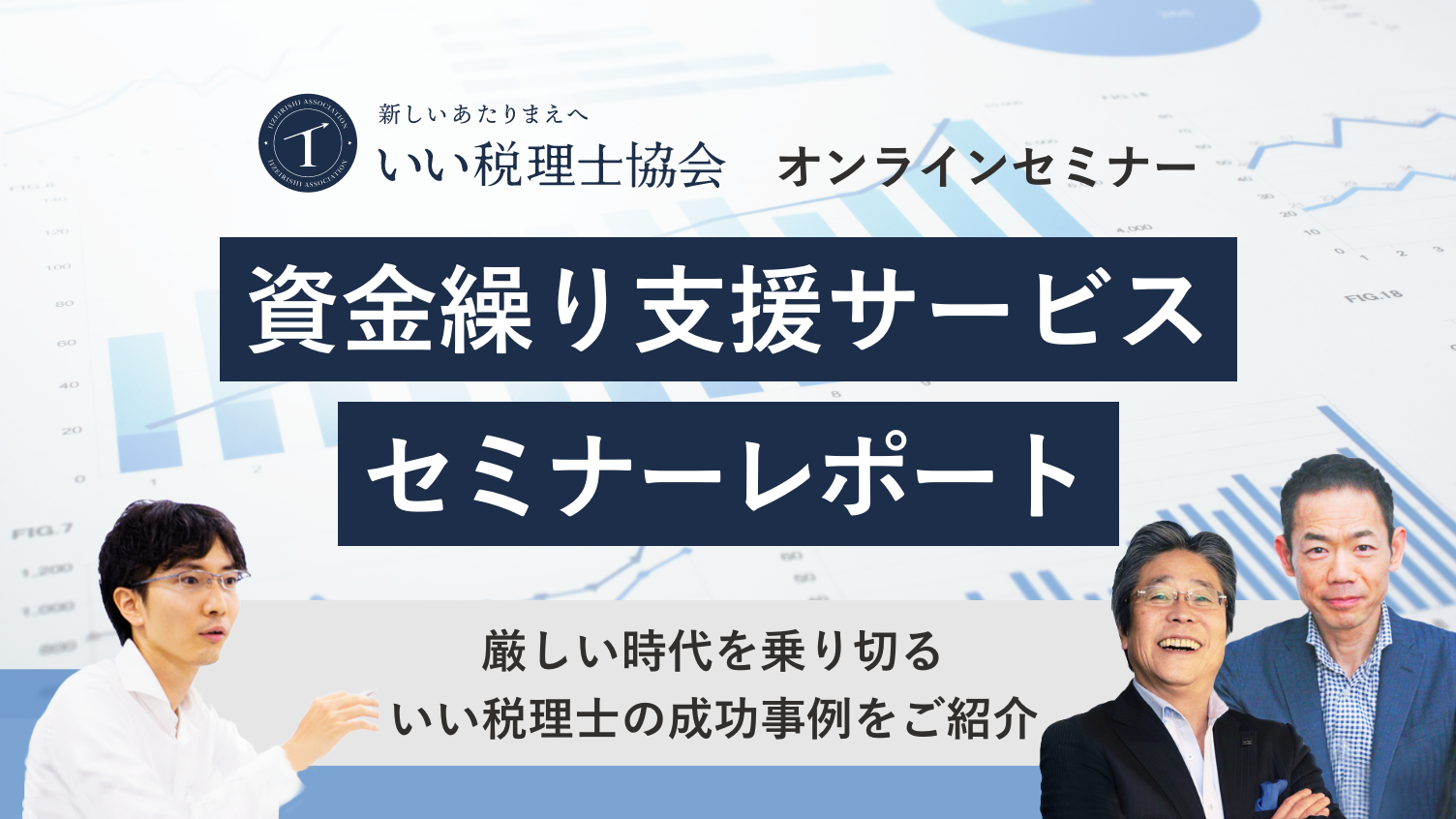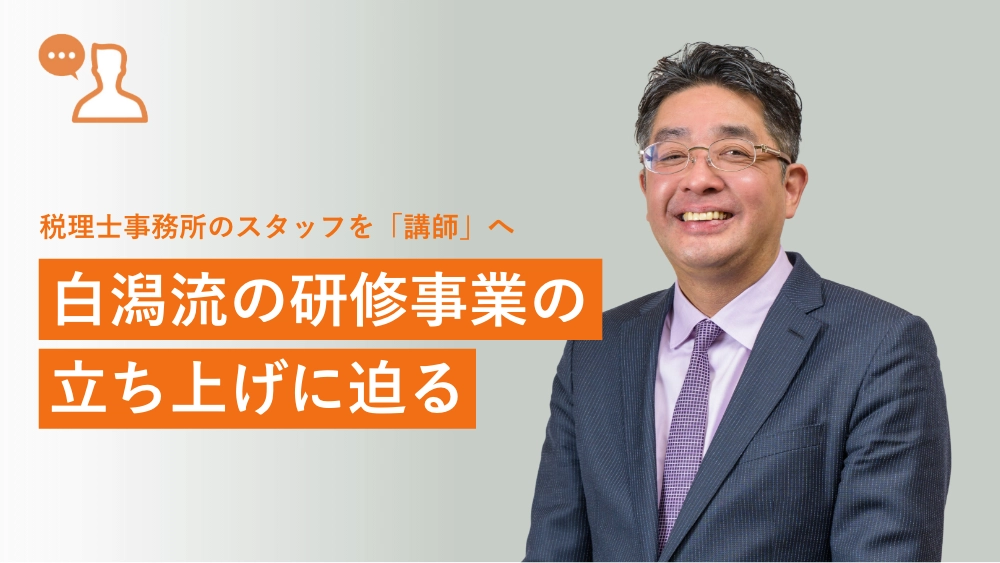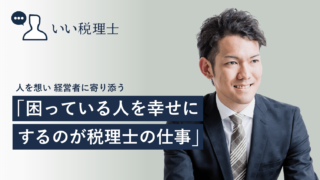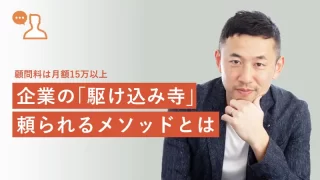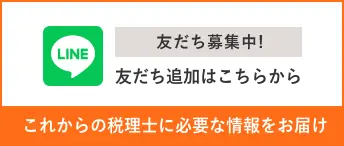【セミナーレポート】「いい税理士」が実践する 採用を成功させる4つのポイント
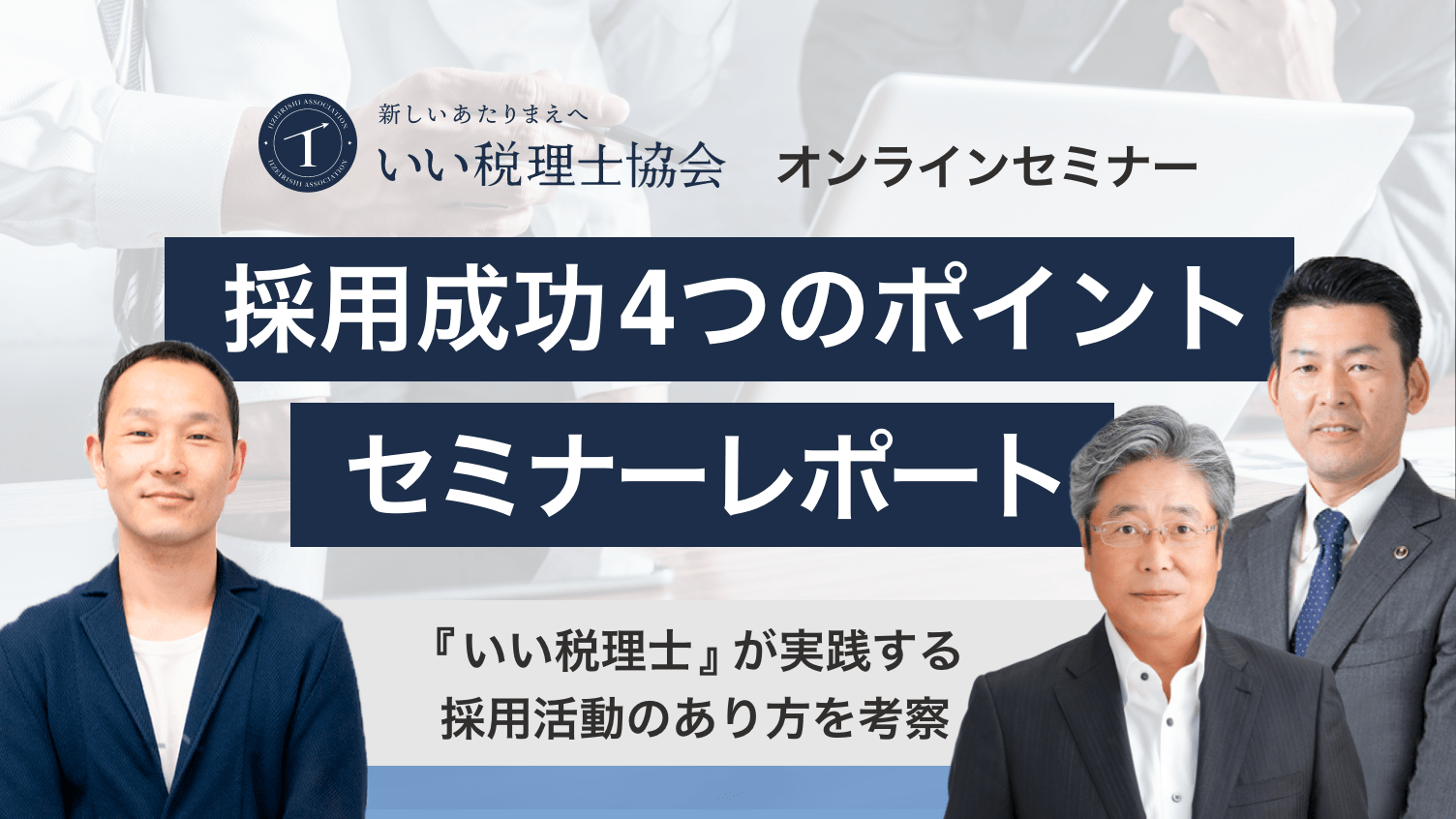
いい人を採用できない、採用してもすぐに辞めてしまう――。そんな悩みを抱える税理士の方は少なくないと思います。そもそもご自身の事務所にとっての「いい人」とはどんな人なのでしょうか?その点も含め、税理士事務所における採用活動のあり方を考察するため、いい税理士協会は7月8日、「会計事務所は『人』がすべて!『いい税理士』が実践する採用手法とは?」と題したオンラインセミナーを開催しました。本記事では、採用に関するノウハウが示されたセミナーの内容をレポートします。
採用すべきは「いい人」ではなく「合う人」
今回のセミナーは2部構成で行われました。第1部には、いい税理士協会代表理事の田中啓介さんが登壇。冒頭で人材採用に関する4つの問題提起をしました。
- ハローワークや税理士会に求人を掲載するだけになっていないか?
- 何の準備もせずに面接に臨んでいないか?
- 面接がこちらからの質問タイムになっていないか?
- 候補者もあなたを面接していることに気づいているか?
これらを意識していないと良い採用活動はできないと指摘する田中さん。そのうえで、会計事務所にとって最も大切な資産である「人」に対して、時間とお金をきちんと投資するように勧めます。
まず1については、「お金をかけずに良い人材を採用するのは難しいため、求人媒体や人材紹介会社の利用を検討するとよいでしょう。採用した人の年収の10~40%程度の報酬を払うことになりますが、必要経費だと割り切ることが大切です」と田中さん。
また4については、「ご自身が候補者を見定めるのと同じように、候補者もこちらを見極めようとしています。面接での上から目線の発言は厳禁です」と指摘します。
2と3についてはさらに具体的な言及があったので、順を追ってみていきましょう。
2の準備に関連して、「そもそも『いい人』を採用したいという漠然とした考えは捨てなくてはなりません。ある税理士にとってのいい人が、別の税理士にとってはいい人ではないということは起こり得るからです。そうではなく、自分の事務所に『合う人』を採用するという発想に切り替える必要があるのです」と田中さんは話します。
ここで言う「合う人」とは、知識やスキル、税理士としての実務経験を持っている人ではなく、次の3点を満たしている人を指します。
- 事務所の理念や方針に共感してくれる人
- 事務所が大切にしている価値観に理解のある人
- 代表税理士をリスペクトしてくれる人
この3点よりも知識やスキル、税理士としての経験を持つ人を優先的に採用すると、次のような弊害が生まれ、採用後のマネジメントコストが膨らんでしまいます。
- 離職のリスクが高い
- マネジメントしづらい
- モチベーションが低い
- 考え方や志向性が異なる
- 事務所の一体感が生まれない
反対に「合う人」を優先的に採用すると、次のように真逆の効果が期待できます。
- 離職のリスクが低い
- マネジメントしやすい
- モチベーションが高い
- 考え方や志向性が同じ
- 事務所の一体感が生まれやすい
つまり採用後にその人にかかるマネジメントのコストが低く抑えられるのです。「合う人」は知識や経験やスキルが足りないかもしれませんが、マネジメントにかかるコストは低いので、事務所のスタッフはその人を教育することに専念できます。
「合う人」を採用するために準備しておくこと
では、「合う人」を採用するには具体的にどうすればよいのでしょうか?田中さんは次の3点が大切だと指摘します。
(A)事務所の理念(ミッションやビジョン)は明確か?
(B)事務所の価値観(行動指針やバリュー)は明確か?
(C)面接で自分のことや事務所のことを語っているか?
特に(A)と(B)が固まっていないと「うちの事務所に合うのはどんな人か」を定義できないため、良い採用活動は難しくなります。例えば、第2部に登壇した高橋保男さんが所属するみそら税理士法人では、事務所のミッションを「経営に『晴れ』のよろこびを。」と定めています。このミッションを一目見ただけで、税務申告や記帳代行だけでなく、企業の業績向上に貢献しようとする事務所であることがわかります。このミッションがスタッフの間に浸透しているため、事務所がどこに向かうかという方向感が定まりますし、事務所の一体感も醸成しやすくなります。同時に、新たな人材を採用する際にも、「合う人」かどうかを見定める基準として機能しています。
そして面接で熱く語ったことに共感しない候補者や、MVVを聞いても志望度が上がらない候補者は、そもそも「合う人」ではないため採用すべきではないと田中さんは指摘します。第一に「合う人」かどうかを見極め、そのうえで知識やスキルや経験を考慮すべきなのです。
一方で、多忙な税理士のみなさんは「合わない人」と面接する時間は持ちたくないと思います。そうしたミスマッチを防ぐための施策にも田中さんは言及しました。
採用に積極的な税理士事務所の共通点
第2部には前述したみそら税理士法人の高橋保男さん(パートナー税理士、神戸統括)と株式会社本宮会計センターで代表取締役を務める鈴木正人さん(いい税理士協会認定 上級会員)が登壇しました。
現在、42名が所属するみそら税理士法人では、パート従業員も含め、可能な限り事務所のスタッフ全員が面接官を務めるそうです。一方、本宮会計センターでは、新卒採用を重視していると言います。両事務所はどんな採用活動を行っているのでしょうか。
面接は「仲間探し」の場
全員面接を実施するみそら税理士法人では、「面接は審査というよりも仲間探しの場だととらえています。「全員面接は『こんな事務所ですが、どうですか?』とざっくばらんに問いかけるために行っています」と高橋さんは話します。
現在の採用方法としては、次の2つのことを行っています。
- 人材紹介会社の利用
- 事務所のホームページでの募集
スタッフの半数以上が新卒採用
25名規模の本宮会計センターでは、実に15名のスタッフが新卒からの採用です(第二新卒も含む)。「中途採用が多い税理士業界において新卒採用にこだわるのは、離職率が低いからです」と鈴木さんは説明します。
現在の採用方法としては、次の3つのことを行っています。
- 新卒採用:求人媒体の利用
- 中途採用:地元(福島県)の人材紹介会社の利用
- 事務所のホームページでの募集
新卒に関してはインターンシップを導入しており、顧問先の許可を得たうえでインターン生もフロントスタッフに同行して顧問先を訪問しているそうです。
採用に積極的な両事務所の共通点
異なる特徴を持つみそら税理士法人と本宮会計センターですが、例えば次のような共通点もあります。
-
- MVVがスタッフの間に浸透している
- 経験を重視せず、異業種からの参入者を歓迎している
- 人材紹介会社の担当者と密接な関係を築いている
- 採用についても、今いるスタッフの意見を大切にしている
特に4については、「入社後に育成に当たるのはスタッフですので、代表である自分の意見よりも、現場に精通するスタッフの意見が決め手になります」と高橋さんも鈴木さんも声を揃えます。このあたりが事務所の規模拡大のポイントなのかもしれません。
また、両事務所はホームページにMVVを明記することで、「合わない人」からの応募を減らす点も共通しています。
* * *
以上、ここでは人材採用のポイントを説明したうえで、採用に積極的な二つの事務所の事例を通して税理士事務所における採用活動のあり方について考察してきました。
今回のセミナーは、経営参謀として経営者に伴走する「いい税理士」の創出を通して、中小企業が躍動する社会を目指す「いい税理士協会」が主催したものです。協会のホームページでは、ここで紹介したセミナーなどの情報を随時更新しています。
※ いい税理士協会は2020年7月をもって解散しました。
この記事をシェアする