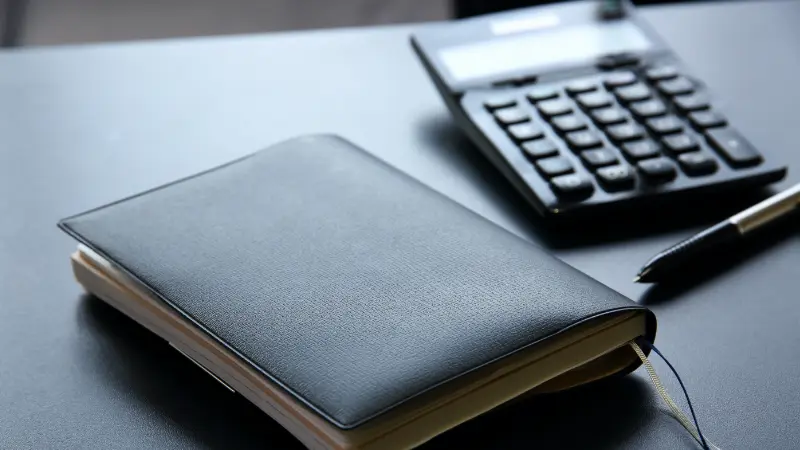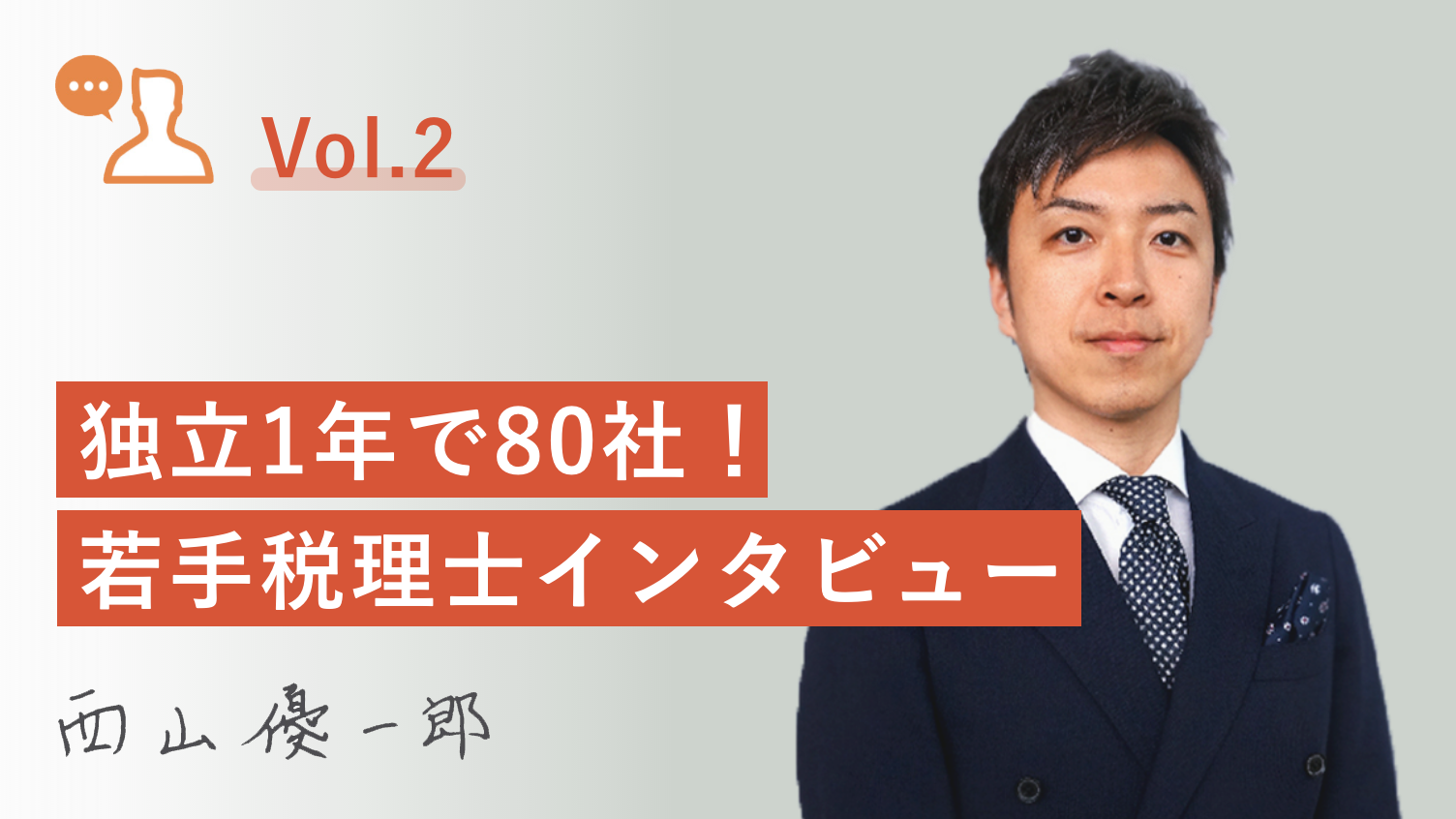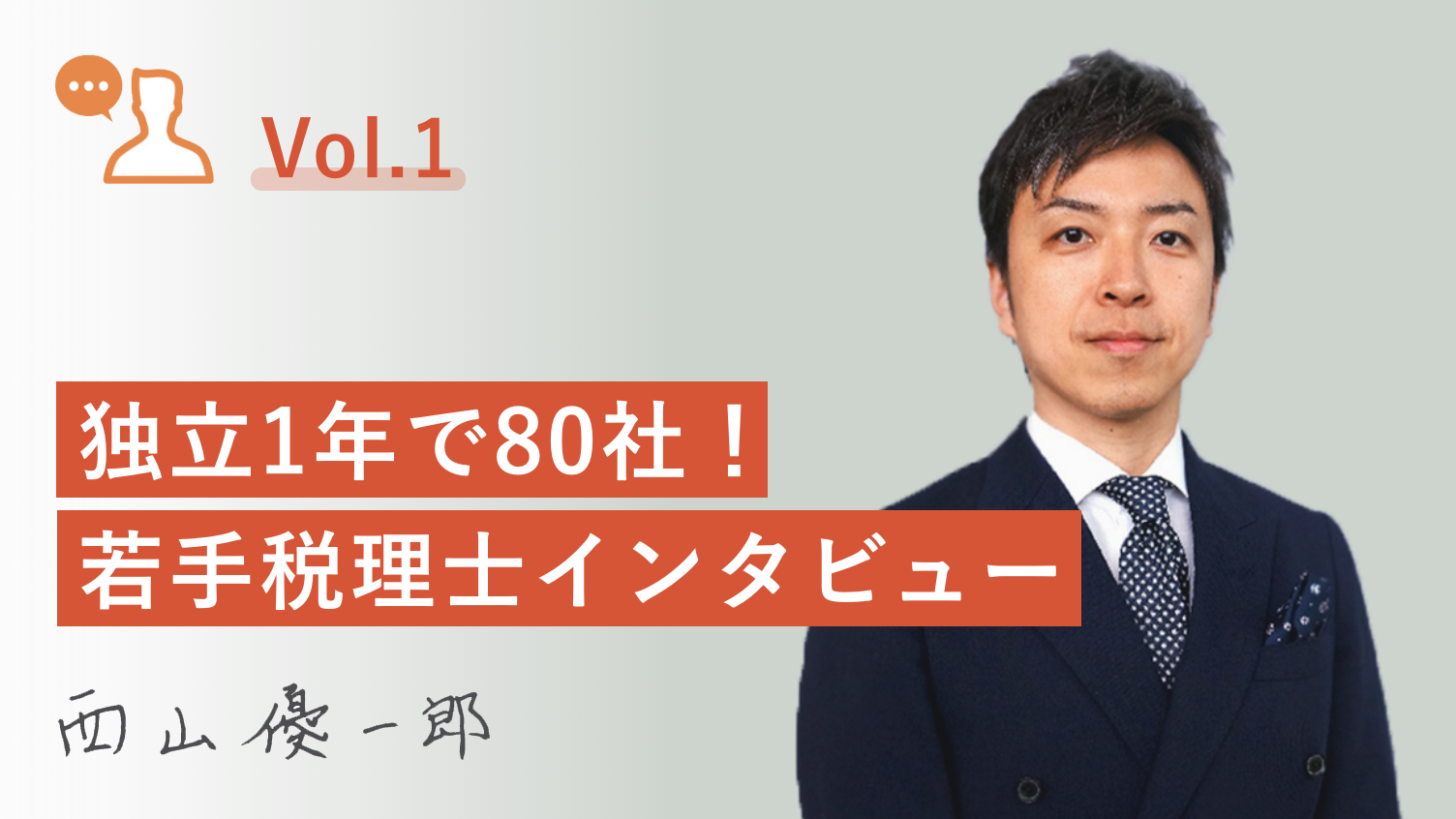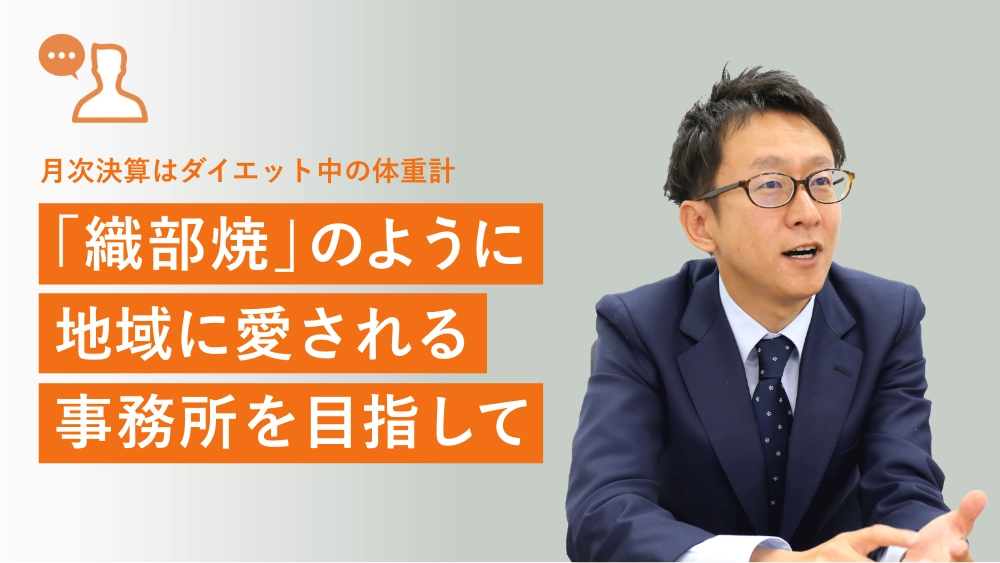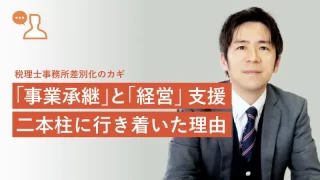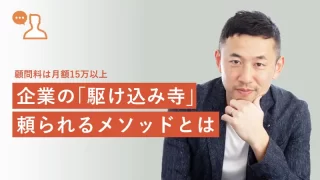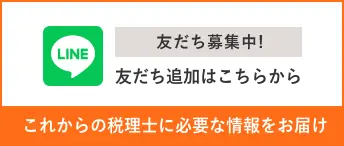税理士の仕事内容とは?業務の内容や税理士の役割をわかりやすく解説!

税理士という職業は普段の生活では接する機会が乏しいため、税理士志望者でもその仕事内容を詳しくは知らないという方も多いでしょう。そこで、この記事では税理士志望者に向けて税理士の役割や仕事内容、年間の業務サイクル、一日のスケジュールを解説します。
税理士とは?役割と税理士制度について
税理士とは、納税義務者をサポートする税の専門家です。
現代の社会は税制が非常に複雑なため、一般市民が働きながら仕組みを理解することは容易ではありません。
税理士はそうした納税義務者に代わって税の仕組みを理解し、人々の納税をサポートする専門家です。
税理士の役割
税理士法第一条では税理士の役割を以下のように説明しています。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(出典:税理士法第一条)
かみ砕くと、税理士の役割とは公正な立場から納税義務者の相談に応じ、納税をサポートすることであるというのが分かります。
上記の役割に基づき、納税義務者からの相談や申告の代理をサポートするのが主な業務となりますが、事務所によっては顧問先の資金調達や事業計画の策定など、経営支援にも取り組んでいる事務所も珍しくありません。
税理士になるには
税理士になるには、毎年実施される税理士試験に合格したうえで2年間の実務経験を積むことが必要です。
税理士試験では全11科目の中から5科目に合格する必要があります。科目は選択必須科目と選択科目にわかれており、毎年受験する科目を自分で選ぶことができます。
税理士試験は数ある資格試験の中でも特に難関の試験として知られており、5科目の合格までに5年以上かかることも珍しくありません。
そのため、多くの受験生は税理士試験の勉強と並行して税理士事務所や税務署で働き、実務経験を積んでいくのが一般的です。
税理士の仕事内容
税理士の仕事は税理士としての独占業務とそれに付随する業務から構成されています。税理士といえば、税の計算だけをしていると思われがちですが、実際には記帳代行などの業務もこなしていかなければならないことを押さえておきましょう。
税理士の独占業務
税理士には法律で定められた三つの独占業務があります。
| 税務代理 | 納税義務者に代わって税金の申告や税務調査のときの主張や陳述を行います。 |
| 税務書類の作成 | 納税義務者に代わって税務署に提出する書類を作成します。 |
| 税務相談 | 税務署に提出する書類や税務調査があった際の主張や陳述などの相談に応じます。 |
これらの業務は税理士の独占業務として法律で定められており、税理士以外の者が行った場合には2年以下の懲役または100万円の罰金が課されるため、税理士だけが担当することになります。
独占業務以外の業務
独占業務の付随業務では記帳代行や給与計算などの業務を行いますが、事務所によっては資金繰り支援や事業計画書の策定など、経営支援を行っているところもあります。付随業務は独占業務の範囲外の業務となるため、特に記帳代行や給与計算などの業務は税理士補助や税務アシスタントが中心に対応し、税理士が後から確認をしていくことになります。
なお、税理士法第2条第2項では税理士が税理士という名称を用いて会計業務を行うことができると解説されており、国税庁のQ&Aでも税理士業務に付随しない会計帳簿の記帳代行などを行っても税理士法違反にはならないと解説されています。
税理士の1年間の業務サイクル
税理士の1年間の業務サイクルは閑散期と繁忙期に分かれています。
時期によって業務量にかなりの差があるため、入所前にそれぞれの時期の業務を押さえておきましょう。
まず、6月~11月は税理士事務所の閑散期にあたります。
この時期は記帳代行や巡回監査、月次決算などの通常業務のみを進めていくことになるため、残業が少なく、定時退社できることがほとんどです。稀に税務調査などの臨時業務が発生することもありますが、時間的な余裕があるため、新人教育などに注力する時期でもあります。
12月~5月は税理士事務所の繁忙期にあたります。
繁忙期は通常業務に加えて年末調整や確定申告、決算申告などの業務を次々にこなしていかなければならないため、かなりの長時間労働を求められることも珍しくありません。
税理士の一日のスケジュール例
税理士の仕事内容のイメージがつかめたところで、実際の税理士の一日のスケジュールを見ていきましょう。実際の業務時間の割り当てや退社時間などについては時期や役職によっても大きく異なりますが、ここでは閑散期の所属税理士を想定しています。
| 8時~9時 | 出社 |
| 9時~9時30分 | 朝礼・業務開始 |
| 9時30分~12時 | 月次作業 |
| 12時~13時 | 昼休み |
| 13時~16時 | 月次訪問 |
| 16時~17時 | 税理士補助の作業確認 |
| 17時~18時 | 事務所にて新規案件の対応 |
| 18時~18時30分 | 退社 |
8時~9時 出社
近年ではフレックスタイム制を導入している事務所も増えつつありますが、ほとんどの事務所では9時~10時の間に始業します。
9時~9時30分 朝礼・業務開始
始業後は初めに全員で朝礼を行います。税理士事務所では各従業員が別々の作業を個々人で進めていくことになるため、朝礼で全体の状況を共有し、その日にやるべきことを口頭で報告します。
9時30分~12時 月次決算作業
月次試算表をもとに月次決算書の作成を行います。
月次決算書はときには金融機関からの融資の可否を判断するための資料として使われることもあります。
12時~13時 昼休み
大抵の場合は時間通りに昼休みをとります。次の予定が月次訪問の場合は昼休み中に移動します。
13時~16時 月次訪問
顧客である顧問先に赴いて資料の受け渡しや節税の提案などを行います。
ときには顧問先から設備投資や資金調達など、経営に関するアドバイスを求められることもあります。近年では在宅ワークが増えた影響でリモートで訪問をする事務所も増えました。
16時~17時 税理士補助の作業確認
事務所に戻り、税理士補助や税務アシスタントに依頼していた作業を確認します。
17時~18時 事務所にて新規案件の対応
日によっては税理士事務所に訪れた新規のクライアント対応をすることもあります。
18時~18時30分 退社
月次訪問を行った場合はそこで話した内容を議事録にまとめます。月次訪問の担当者が変更になることは稀ですが、担当者の都合によっては別の者が担当することもあるため、社内共有用に記録を残すのが一般的です。
税理士資格を取ることで選択できるキャリア
税理士となることで選択できるキャリアは税理士事務所だけではありません。ここでは税理士資格を取ることで選択できるキャリアについて解説します。
事務所への就職
税理士事務所に就職するケースでは税理士登録に必要な実務経験を積むために税理士補助や税務アシスタントなどの職種で入所し、試験合格後にそのまま税理士として勤務するパターンと他事務所に転職するパターンがあります。
将来的に独立や一般企業への就職を検討している場合でも、まずは税理士としての実務経験を積むために税理士事務所に就職する方も多くいます。
なお、事務所によっては税理士が経営している事務所でも会計事務所の屋号を用いている場合もあります。
これは日本の法律では税理士が会計事務所という屋号を使って開業しても問題ないことになっているためで、業務内容に違いがあるわけではありません。就職する際は業務内容をもとに判断するようにしましょう。
事業会社への就職
税理士資格を活かして事業会社に就職するケースでは経理財務部門に配属される場合が多く、財務会計または管理会計を担当するのが一般的です。
求められる能力は会社の成長ステージや就職時の年齢によっても異なります。
例えば、30代で転職する場合は非上場企業では管理部門体制を整備できる力が求められ、上場企業では豊富な法人税務の経験と高い英語力、国際税務などの専門知識が求められることもあります。
独立開業
税理士として開業するケースです。
税理士資格を取得することで税理士事務所を開業することもできます。
顧問先や業務内容を自分で選べるため、自らが望む専門性を磨くことができるのが魅力です。
働く場所や時間を自分で選べるので、子育てや介護とも両立しやすく、自分に合った働き方をすることができます。
ただし、独立すると福利厚生や有給休暇を利用することができなくなったり、事務所を軌道に乗せるまでには営業力が求められたりするため、事前の計画が重要です。
これからの税理士に求められること
税理士事務所の顧問料は年々減少の一途を辿っており、将来的にはAIに仕事の一部が代替されることが予想されています。
記帳代行を中心とした従来型の事務所経営では立ち行かなくなることも考えられるため、付加価値の高いサービスを模索し、顧問先である中小企業に提供していくことが求められています。
freeeでは、顧問先の業績向上に貢献している税理士へのインタビュー記事や事務所経営に役立つ記事など、多数配信しています。ご期待ください。
この記事をシェアする