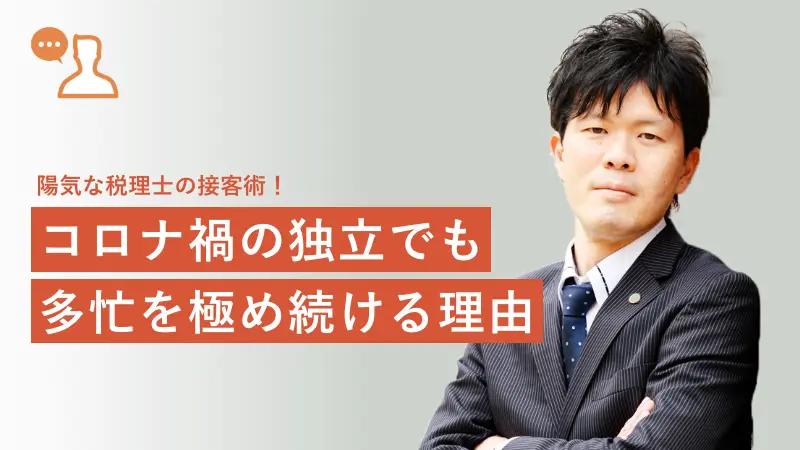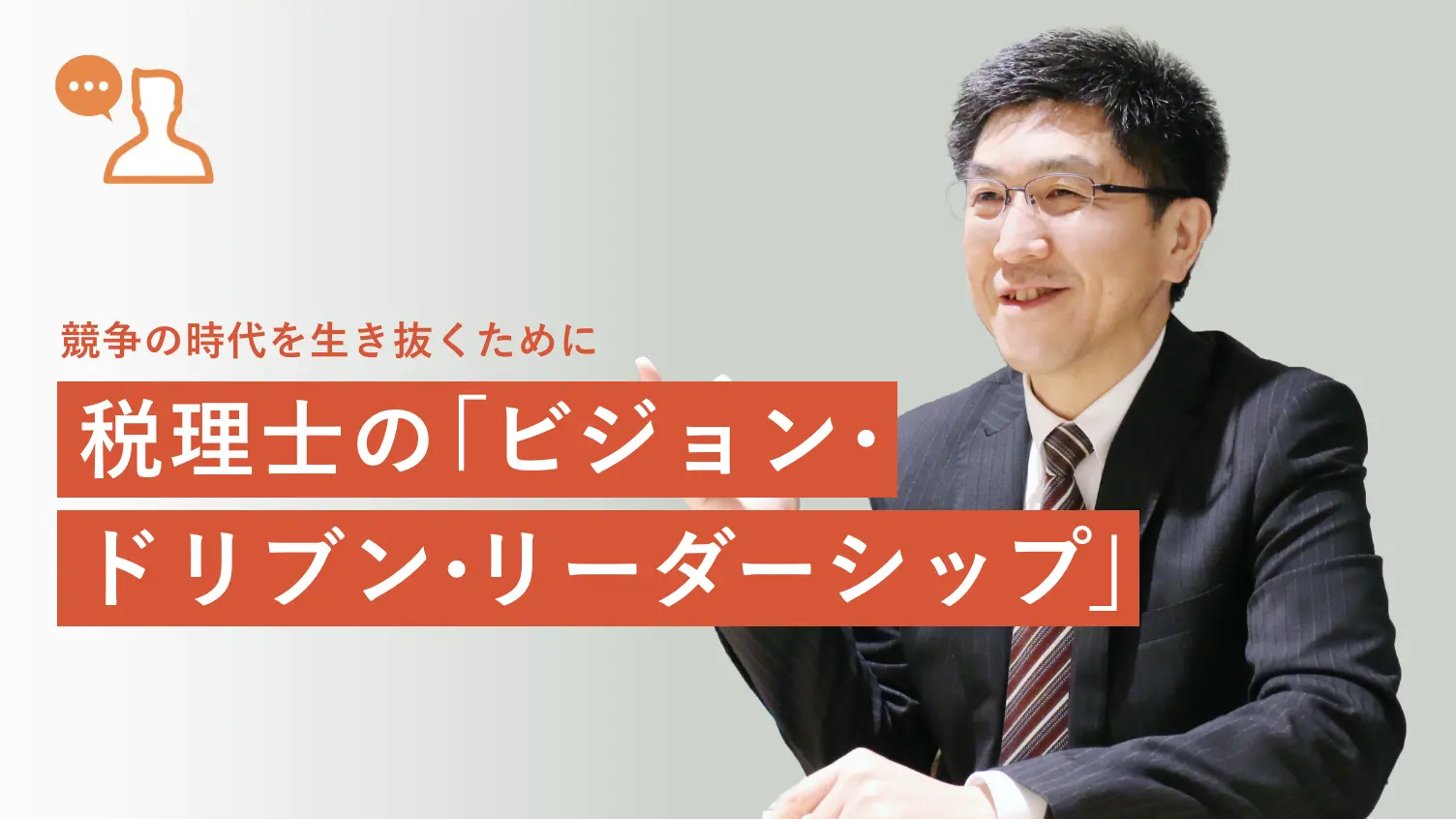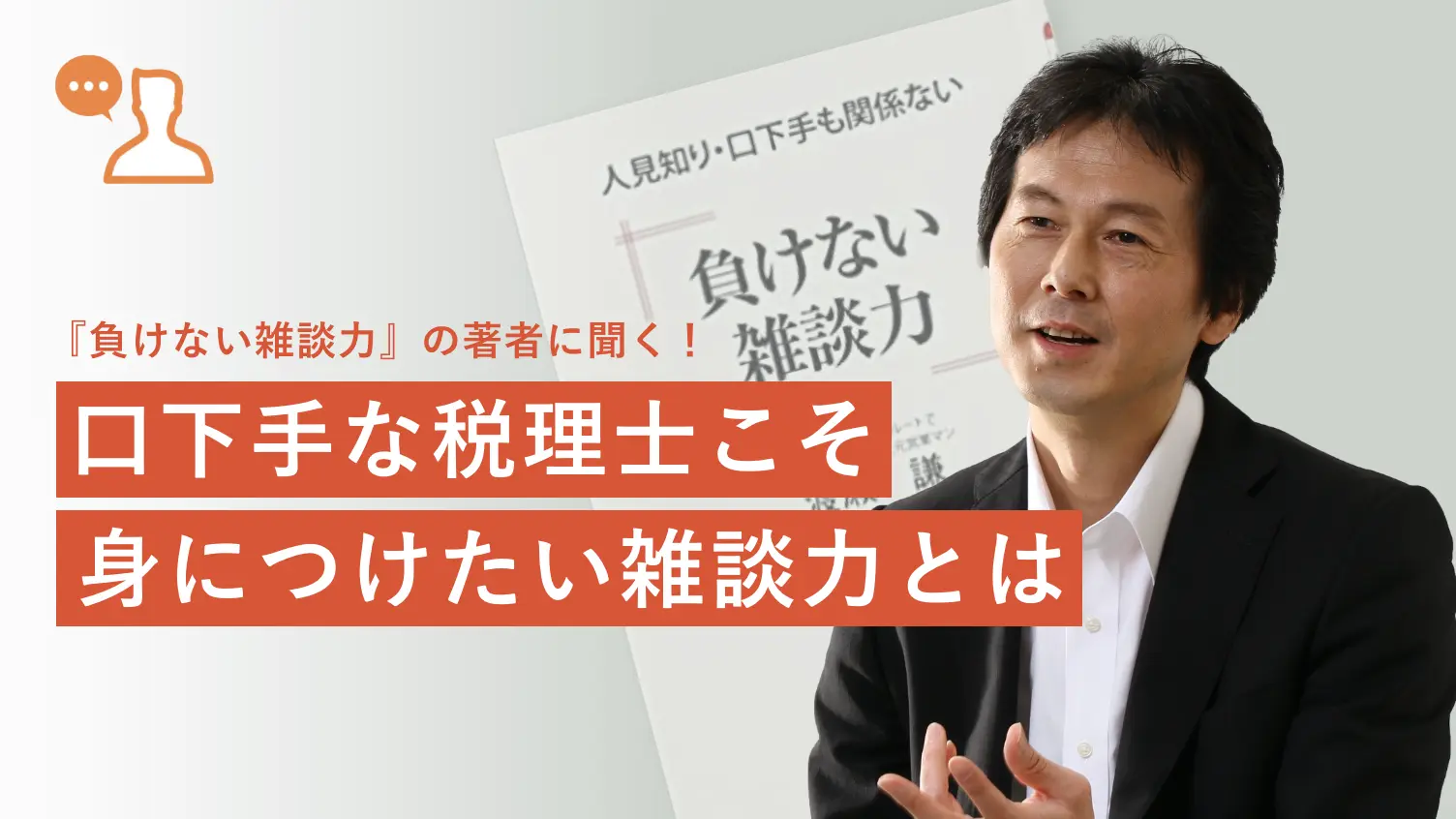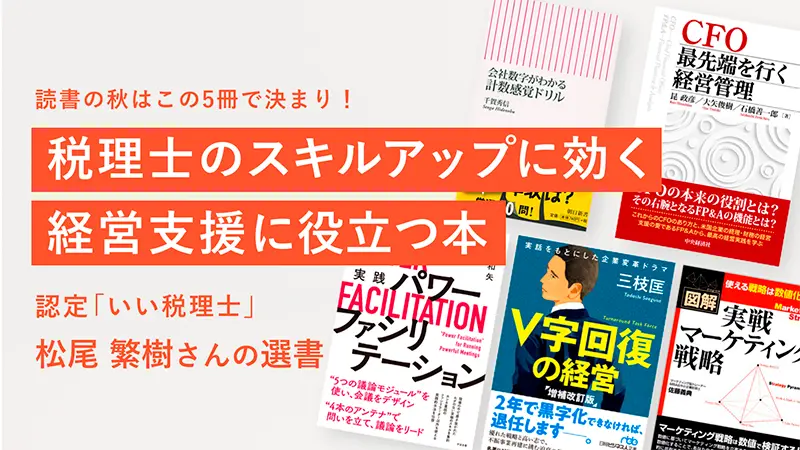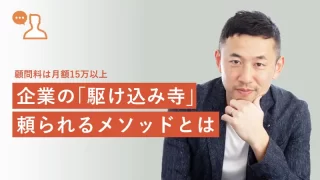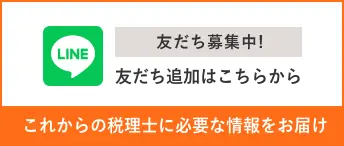税理士として個人の成長だけでは幸せになれない?『7つの習慣』から学ぶ成長モデル

発売から約30年、長く愛され続けている名著『7つの習慣』。人の成功に欠かせない考え方と、達成するために必要な具体的な習慣が書かれた本書は、世界中で約3000万人に読まれています。
前回の記事では、本書の基本となる「人格主義」という考え方を始め、まずは個人的な成功を実現するための第1〜第3の習慣についてご紹介しました。
後編となる本記事では、個人的な成功を手にした人がさらに成長していくための考え方として、第4〜第7の習慣をご紹介します。
人は「依存」「自立」「相互依存」と成長していく
人の成長は「依存」「自立」「相互依存」と三段階あり、順番を飛ばして成長することはできません。
生まれたばかりの赤ちゃんが人の手助けなしに生きられないように、人はまず依存期を通して成長し、そして自分の足で立ち、自分で考え行動する自立期へと成長します。さらに自分ひとりで立てるからこそ、次の段階として周りと手を取り合い支え合っていく相互依存期へと成長していきます。
前編でご紹介した第1〜第3の習慣は人を依存期から自立期へと成長させ、私的成功を目指すための習慣となっています。そしてこれからご紹介する第4〜6の習慣は、人と手を取りあい成長を目指す、相互依存を目指すフェーズになります。
本書ではこれを「公的成功」と表現しています。税理士で言えば、事務所スタッフとの相互依存、顧客である経営者との相互依存はもちろん、家族・友人との相互依存を通して、一人ではなし得ない成功を目指していきます。
そして最後の第7の習慣では、身につけた6つの習慣を継続していくための習慣が書かれています。
それでは、自分一人ではなし得ない成功を手にするために、第4の習慣からご紹介していきます。
第4の習慣「Win-Winを考える」

私達の対人関係には、6つの関係性があると本書では書かれています。
- Win-Win:自分も勝ち、相手も勝つ
- Win-Lose:自分が勝ち、相手は負ける
- Lose-Win:自分が負けて、相手が勝つ
- Lose-Lose:自分も負けて、相手も負ける
- Win:自分が勝つ
- Win-Win or No Deal:自分も勝ち相手も勝つ、それが無理なら取り引きしないことに合意する
引用元:完訳 7つの習慣
相互依存を目指すのであれば、お互いが勝つこと、すなわち「Win-Win」を目指していくことが必要です。
税理士であれば「自分の成功」だけを追いかけるのは、Win-Winとは言えません。なぜなら、自分だけが成功しても顧問先に価値を提供できなければ相互依存とはならないからです。
Win-Winは、人生や人間関係を競争の場と捉えるのではなく、協力の場として捉えることから始まります。私たちはつい何事もどっちが強いか、どっちが優秀かといった二択で考えがちです。しかしこの考え方は原則に基づいておらず、自分の権力や地位にものを言わせる態度だと書かれています。
またどうしてもWin-Winの関係を見つけられない場合、「Win-Win or No Deal」、すなわち取引をしないという選択肢もあります。
お互いの違いを理解し認め、そして何も合意しない。少し高度な選択かもしれませんが、いずれにせよ第4の習慣ではまず、勝ち負けの二軸思考から抜け出すことを伝えています。
第5の習慣「まず理解に徹し、そして理解される」
人は誰しも、人から理解されたいと思っています。しかし人は他者の話を聴くとき、理解に徹するのではなく相手の話にどう返したらいいか、何を次に話そうかといったことを考え、理解に徹せられていないといいます。
第5の習慣では「まず理解に徹し、そして理解される」を掲げ、相手の言葉に対して共感による傾聴を徹底し、深く理解した上で、相手との信頼関係構築を目指す重要性を伝えています。
人は話を聴く際、以下の4つの行為をもって反応していることがほとんどだそうです。
- 評価する–同意するか反対するか
- 探る–自分の視点から質問する
- 助言する–自分の経験から助言する
- 解釈する–自分の動機や行動を基にして相手の動機や行動を説明する
引用元:完訳 7つの習慣
しかしこれら4つの反応を示すことは、自分の自叙伝を語ることであり、相手を理解することからは遠ざかってしまいます。
税理士として真に共感力を発揮し、そして顧客である経営者の中に自分への信頼を蓄積していくためにも、すでにあるコミュニケーションのクセを一度取り除き、本当の意味で傾聴していく必要があります。
>>顧問先に寄り添い、顧問先の経営実行力をいっしょに高めたい
第6の習慣「シナジーを創り出す」
人間関係で生み出す成果が、1+1=5や10や100になるよう、相乗効果を生み出していくことが、第6の習慣の目的です。そのためには相手と自分の間に信頼関係が構築されていること、そしてWin-Winを考える姿勢と共感による真の傾聴力が土台として必要です。
他者を信頼し、安定性のある心を開いたコミュニケーションを取っていくと、お互いに違いを受け入れる「冒険」をすることができます。この冒険の結果、一人では考えつかなかった第三の案、すなわちシナジーを生み出すことができるとされます。
それでは税理士の仕事現場で考えてみましょう。
例えば顧問先とのシナジーを望むのであれば、まずはあなた自身が顧問先から信頼に値する人として成長し、心を傾け向き合っていく。こうした日々の積み重ねの結果、例えばあなたが事務所としてもっと売上を上げていきたいといった悩みにぶつかった時、「知り合いの経営者を紹介しましょうか?」といった第三の解決策を示してくれるかもしれません。
こういった第三の建設的な提案が生み出される関係性が、シナジーの一例です。
皆さんもぜひ、公的成功のゴールとして、人との相乗効果を意識してみましょう。
第7の習慣「刃を研ぐ」

第1〜第6の習慣を実践することで、私たちは人を頼ることで生存できる「依存」の状態から、一人で考え行動できる「自立」へと成長します。そして人と手を取りあい、より相乗効果のある生き方が叶う「相互依存」へと成長していきます。
最後の第7の習慣では、この身につけた6つの習慣を継続するため、あなた自身のメンテナンスをしていく重要性を説いています。
具体的には以下4つのメンテナンスをし、あなたという刃を研ぐことが重要です。
肉体
適度な運動や身体に良い食事、ストレス管理などをおこない、身体を大切にしていく。
精神
自分自身を鼓舞し続けるため、瞑想を取り入れたり偉大な芸術に触れたりして、精神の充実を図る。
知性
継続的に学び、知性を磨き広げていく努力をする。優れた古典文学や自伝、多様な分野の書籍を読む。
環境
共感や相互理解など、現実の人間関係から再度意識し再現していくことで社会や情緒を見直す。
これら4つの刃は、1つを磨くことで他の刃にも良い影響を与えるものです。また刃を磨くことで6つの習慣を実践する能力がさらに高まります。
つまり全てがつながっており、継続的に取り組むことで、ぐるぐると螺旋を描くように私たちは成長していけるのです。
まとめ
7つの習慣について、前編後編2本に分けて内容をご紹介していきました。
税理士の皆さんは、自分自身のスキルアップについて考える機会が多いと思います。ぜひ自分を磨くだけでなく、事務所のスタッフや顧問先、さらには社会との信頼関係や相乗効果といった側面にも目を向けてみると、また大きなシナジーの広がりを感じるかもしれません。
ひとりの税理士として、事務所の成功とは何か、スタッフの成功とは何か、顧問先の成功とは何か、今一度考える機会になるのではないでしょうか。
【紹介書籍】
完訳 7つの習慣
スティーブン・R・コヴィー / 著 2,200円(税別)
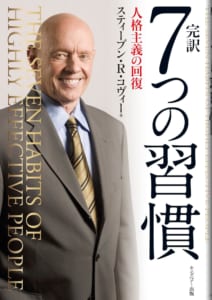
この記事をシェアする